弦楽器広場(3) |
| HOME|音楽室|びよらのつぶやき日誌|リンクの広場|プロフィール|掲示板〜びよらの広場 |
|
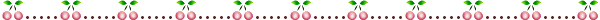 |
 「ボーイング付け」について 「ボーイング付け」について |
オケに在籍していちばん嫌な作業はボーイング決めです。 はっきりとした法則があるわけでもなく またこのボーイングが一番良いんだと言える自信もない上に、本格的な合奏に入るまでには出来上がってなければならない、というやっかいなしろ物だからです。 いただいた楽譜に以前のボーイングが入ってあったり、前に演奏した曲であればある程度助かるのですが、時間的余裕も技術もなく、しかも何の予備知識もなくボーイングを決めるのは本当に辛い作業です。 基本的には自分が弾きやすいことを一番に考えています。 クレッシェンドは【アップ】、ディミネントは【ダウン】が弾きやすいですし、ピアノは自然と先弓になるよう、フォルテは中・元弓になるように。また、速いパッセージや拍の頭は基本的に【ダウン】から始まるように持って行きたいと考えております。 【ダウン】ボーイングは呼吸でいうところの“吐く動作”になります。したがってアインザッツのブレス合わせでは【ダウン】ボーイングが合わせ易くなります。(弾き始めを合わす事を"アインザッツ(ザッツ)を合わす"と言い、管楽器はもちろんの事、弦楽器でも皆で息を合わせる事で出だしが決まるのです) 【アップ】ボーイングは“吸う動作”になるため【ダウン】よりは合わせにくくなってしまいます。 しかしそうはうまく行くはずもなく、壁にぶち当たったときテレビのクラシック番組が大変参考になります。技術のあるプロが我々以上に楽譜に忠実なボーイングをしていること(ppはみごとにppにしかならない弾き方をしており、ffはffにしかならない弾き方をしている・・・弓の位置・使う量など)に驚かされますし、見習わなければならないことです。 応用技術がなく、文字どおり“体で覚える”しかない私にとって、ボーイングが途中でコロコロ変わるのはそれまでの練習を無に帰するに価する事。 ボーイングが決まってるという事は、アンサンブルにも、自分の練習にも最も重要であるのは重々承知してます。 でも、指揮者の望む音楽を表現出来るボーイングが最優先されますし、練習を重ねていくうちに問題点も出てきますので、やむを得ず変更することも多々あるのは避けられない事ですね。 まして、ばよりんにぶら下がったり、ちぇろにくっついたりする、我々“びよら族”にとってのボーイング決めは、パズル以外の何物でもないですよね。(ため息) |
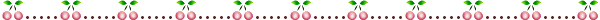 |
 曲のイメージ 曲のイメージ |
指揮者の“曲のイメージ”と同体になるって難しいですね。 極論を言えば、指揮者はピアニストであり、奏者はピアノ鍵盤のひとつひとつなのですが、鍵盤にも主張はありますしね。(“黒鍵はイヤだ。白鍵にしてくれ〜”じゃないですよ) もちろんテクニックの問題で表現出来ない事がほとんどですが、、、 困るのは「この指揮者はどんな表現にしたいのだろうか?」と理解できない場合。 細かな指示は出されるのですが全体像が伝わってこない。 でも、何を言いたいの?と指揮者に疑問を持つ前に、自分自身(奏者側)に勉強不足や譜読み不足がないか、自問自答してみて下さい。 自分なりに曲の全体像を掴んでいないと、部分部分での指示の意味が理解できない場合もあります。 練習中にどこかのパートが指揮者に捕まった時、それを他人事(びよらで良かった〜)なんて思わず、その一言一言の意味を噛みしめましょう。 自分のパートに言われた事はなかなか判らなくても、他のパートへの指示は案外理解しやすいものですよ。 (でもここだけの話)凄い指揮者っておられますねぇ。 棒の動きだけで“何を、どうしたいのか”が見えるんですよね。 決して“振りのテクニック”じゃなく、オーラとでも言うのでしょうか、音符の重さまで伝わって来て、不思議と自分もその音が出てしまうんですよ。 おそらく、その時の自分の“張りつめた集中力”がなせる技でしょうね。 本番がベストの演奏だったというアマオケが多いのも、“もう2度と弾くことはない最後の演奏”にかける集中力の賜ですね。 普段の練習でも体験したいものです。 でも指揮者に引っ張られるだけの私には、言葉の表現力も大いに期待する処であります。 心に残った指揮者の言葉を2〜3紹介してみます。 ♪・・・・・♪・・・・・♪ 駆け上がり音型で、最後の最高音がPP。 どの曲だったか忘れましたが、指揮者がその最後の音の弾き方について 音符というものは繊細で壊れやすいものです。 玉子をイメージして下さい。 皆さんは、背の届かない高い棚の上にその玉子を置かなければならないのです。 今の弾き方は、玉子を強く握りしめ、ジャンプして棚の上に「ゴツン」と飛び乗せてます。 それじゃ、玉子は割れてしまいます。 きちんと“はしご”を掛け、そ〜っと、本当に静かにフワっと棚の上に置いて下さい。 “音符は下から飛び乗せるのではなく、上からそっと置く”というイメージを忘れないで下さい。 ♪・・・・・♪・・・・・♪ 静かなトレモロ部分で(確かドヴォコンの冒頭、Vcソロの出る前) ほら、細かな“霧雨”が降ってきましたよ。 顔に当たっても気にならない、とても爽やかな感触ですよ。 ♪・・・・・♪・・・・・♪ 第九、2楽章の中間部分、オーボエのソロで、 今のソロは大変すてきでした。 でも、途中のスピットピアノ部分で、もっともっと急激な差を出して頂けませんか? 激しい冒頭部分が終わり、こんなにも綺麗な中間部分が聴く者をうっとりとさせてくれます。 でも、このオーボエのスピットピアノは後半の激しさを予感させる、すなわち、聴衆を一瞬「ハッ」と我に帰らさなければならない箇所です。 ベートーヴェンは、そう考えてスピットピアノにしたんだと思うのです。 今のスピットピアノはたいへん心地よいものでした。 でも“奏者自身が理不尽に思うほどの差をつけなければ”予感は出来ないと思います。 おまけ 弓の毛3本で弾いて下さい。 |
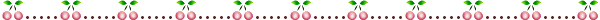 |
 アマオケの運営について アマオケの運営について |
転勤で様々なアマオケにお世話になり、また自ら運営に携わってきた時期もあり、アマオケ運営の難しさ・辛さはイヤと言うほど体験してきました。 ごく平均的なアマチュアオケしか知りませんが、様々な人が70名以上も集まって一つの事に取り組む事の難しさは並大抵ではないですね。 会社なら「役職」大学オケなら「先輩後輩」の力関係もあり、タテ系統の号令一発で事は済みますが、アマオケではそうは行かないですから。 殆どの場合“ごく一部の方”が寝食をも忘れ、プライベートの全てを捧げるという事に支えられて運営が成り立つ、というパターンではないでしょうか? 私も、練習場探し・練習計画造りに始まり、客演奏者・指揮者探しにギャラ交渉、曲決めから楽譜探し、団内誌発行(この時作った原稿のお陰でこの弦楽器広場が成立してる訳ですが)練習の進行役に至るまで、多くの方に助けて貰いつつ、4年間インペク(インスペクター:オケの何でも屋)を努め、精も根も尽き果てた過去があります。 運営経験のある方は良くお判りだと思いますが“上手くいってあたりまえ”、みんなの事を思って何かをするにも(しようと思うにも)“何でそんな事するんだよ”という批判の声はバンバンあがりますし。 4年間の経験から、インペク業は「嫌われてナンボのもん」という境地に達しました。(汗) 全員が満足する道はありませんので“出来るだけ大勢”の満足が得られる道を選択し、決定するという“決断力”が不可欠と、私のインペク時代の後半は嫌われまくったと思います。 一番迷ったのは、その“出来るだけ大勢”というのが、どのレベルか?という事。 概して、管楽器の方は楽器歴も長く“オケでソロを吹くべ(←北海道弁)”という強者揃いですから、例えば曲決めの時や練習が上手く進まない時の声も大きく、初級・中級の弦楽器の声をかき消してしまうケースもありました。(そんな事ないべ、と言われる方にはごめんなさい) 当然シートが確保されるか否かの大問題ですし、演奏会までの長い時間、毎回ボーっとイスに座ったまま、楽器が冷えないように息を吹き込む“待ち”が続く事は、元ボントロ吹きの私も重々承知です。 ただ、もし初心者弦楽器奏者の多いオケでしたら“弾きたくても弾けない”状況の辛さはその比ではないので、私はそういった弦楽器のレベルに合わせた運営を意識してました。 “そんな状態の人、オケはまだ無理だよ”という声もありましたが、それではオーケストラにはならないという現実もありましたし・・・ もっとも楽器未経験の方の入団問い合わせには“最低2〜3年レッスンについて基礎を学び、それから声を掛けてください”とお答えしてましたが。 もうひとつのレベル合わせ・・・出席率の問題もアタマを悩まされた事です。 会社や大学オケとは違い、不特定多数の社会人の集まりなので仕事や家庭事情は様々。 ですから、練習時間帯や練習曜日の変更は、余程の事情がない限りやってはいけない事と決め、それを踏まえた上で“出席”に関しては、必ず事前連絡して下さいと、“無断欠席”だけは厳禁にしてました。 あと心がけていた事は、練習時間内になるべく多くの団員の方に声を掛ける事。 特に入団してまだ日の浅い方には「○○さん」と名前を呼んで話しかける事は運営側の心得としては大事ですね。 どれだけ充実した練習時間が過ごせるか?が、運営の最大の目的であり、その為の演奏会計画・曲選び・指揮者探しをしてました。 でかい曲を演りたい、有名な指揮者で演りたいという声も大きかったですが、本番間際に客演奏者や本番指揮者が揃って、ようやく曲らしくなる、ってのは余りにも寂しすぎますしね。 『アマオケは毎回の練習が“全て”であり、演奏会はその延長にすぎない。』と言うのが私のアマオケ活動に対する持論です。
| |
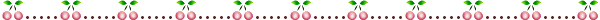 |
 クラシック音楽界への一考察(独断と偏見) クラシック音楽界への一考察(独断と偏見) |
日本ハムファイターズの試合をドームへ見に行く機会がありました。 試合直前のドーム練習では、例の「5レンジャー」が見れましたし、新庄選手の幻のさよならホームラン(田中選手と2塁付近で抱き合って、走者追い抜きで2塁打となった)も出ました。 プレーオフを掛けたダイエー戦だったので観客も相当多いだろうと、かなり早めにドームに着きましたが、席取り並びは友人がしてくれると言うのでそれに甘え、ドーム裏側の練習場に選手達のウォーミングアップを見に行きました。 ファンの子供達の「サイン下さ〜い」という呼び声に手を振りながら、みんな走り込みや柔軟を続けてました。 その中で1人黙々とファンの人達にサインをし続けている選手がいるのに気がつきました。 最後の1人まで、ずっとサインを続け、「もう他にはいませんね」と、その場を離れるまで都合1時間以上。 それをずっと眺めていた私も私ですが、試合前の大切な時間に1時間以上もファンサービスを続けていたその選手の素晴らしさ。 友人が「エースの金村選手ですよ」って教えてくれました。 年末に放映した「波瀾万丈・新庄選手特集」で、新庄選手は“カエル”“スパイダーマン”そして私も見た“5レンジャー”のかぶり物について、こう語ってました。 「どうしたらドームを満員にできるか?を必死で考えてます。かぶり物も、1人でも多くのお客さんが球場に足を運んで下さるように、と考え抜いたものです」 そして、1月5日のつぶやき日誌にも書いた話、 > メジャー時代の新庄選手の通訳をされていた小島さんから、こんな新庄選手のエピソードを聞かれたそうです。 > 試合後「小島さんの車」で球場から出ようとしたら、その車が汚れていたそうです。 > 「小島さん、球場を一歩出れば、ファンが待っているんだよ。 > 汚れた車に乗っているのを見たら、ファンががっかりするよ」 > と、なんと新庄選手は自ら車を洗車し出したそうです。 > 当然、小島さんもゴシゴシといっしょに車を洗ったのですが、洗い終わって、 > なんと新庄選手は > 「ありがとう、小島さん」ってお礼を言ったそうです。 松井選手はどんなに疲れた時も、どんなに成績が悪かった時も、インタビューには必ず応じるそうです。 そのマイク・カメラの向こうに大勢のファンの方が居るから、だそうです。 昔、団員の方の口添えで、あるプロオケのステージリハーサルを見せてもらえる機会に恵まれました。 ジャマしちゃいけないと、客席の最奥部の隅で静かに座ってたのですが、ステージ上から他の団員に「誰だ?きさま!出てけ!」と叫ばれ、犬でも追い払うような仕草で追い出された事がありました。 気分が乗らないからとドタキャンする事で有名な奏者もおられますし、子供が小学生の時、いっしょに演奏会に行って、入れて貰えなかった事もありました。 音楽を生業とするまでには想像を絶する苦労があり、犠牲にしてきた事も数限りなくあっただろうと思います。 趣味として音楽を捉える我々と、仕事として音楽を捉えるプロの方々とは根本的に違う事は承知しますが、プロ野球選手のここまで徹底したファンサービス、、、 「見て楽しむもの」と「聴いて楽しむもの」、野球とクラシック音楽を同じ目線で見る事は間違ってると言われるかも知れませんが、プロとして「どれだけファンを広げられるか?」という熱意、ファン(観衆)あってのプロであるという意識の差、、、 もちろんこの事は、我々アマチュアにも言える事です。 金額の多少はあるにしろ、アマオケも演奏会には入場料を取るわけですし、お金を払って聴きにきて下さるお客様には、少なくとも舞台の上では我々もプロですから。 私の所属団体も遅まきながら次回演奏会から「終演後のお客様のお見送り」をする事になりました。 ホール退去時間との兼ね合いで、終演後は慌てて着替え、舞台のイス・譜面台・山台の撤去、受付の片づけ等に追いまくられてましたが、全員すぐにロビーへ駆けつけ「ありがとうございました」とお客さんをお見送りしましょうという事に。 大賛成です。 クラシック界も、最近はファンとの交流会も増えてきましたし、昔ほど「高級な近寄りがたいもの」というイメージは薄れてきたとは思います。 クラシック界の底辺が広がっていく事を期待したいですし、我々も微力ですが努力していきたいですね。 |
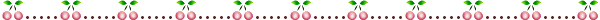 |
 調性の色 調性の色 |
05.5/15放送のN響アワー「24色の音パレット」を見ましたか? 例によって日曜の夜は“羽田→千歳”の空の上ですので、録画してたのですが、 遅くに「見ながら寝るとしようか」と何気にビデオのスイッチを入れたら、そのまま画面(音?)に釘付けになってしまい、3回も見直してしまいました。 調性が持つ“色”というか“雰囲気”というか、その調が表現するイメージを、判りやすく同じ調の演奏画面(いずれもほんの10秒程ですが)をつなげて解説してくれました。 まずハ長調 ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第4楽章 シューベルト 交響曲第9番「グレイト」第1楽章 ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 続いてハ短調 ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章 サンサーンス 交響曲第3番「オルガン付き」第2部 マーラー 交響曲第2番「復活」第1楽章 ホ短調 ブラームス 交響曲第4番第1楽章 チャイコフスキー 交響曲第5番第1楽章 ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」第1楽章 変ホ長調 ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」第1楽章 ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」第1楽章 モーツァルト 交響曲第39番3・4楽章 マーラーとモーツァルト以外は過去何度も演奏した曲です。おそらく何十時間もそれぞれの譜面とにらめっこしてたはずです。 同じ調性だと意識した事もなく、ましてこんな風に並べて聴くのは初めて。 “衝撃”でした。 確かにそれぞれの調性に共通した“明確な色”があるんです! 専門に勉強された方には「なんだ、そんなこと」と言われるかも知れませんが、耳学問と体で覚えた私にとって、この“色”はカルチャーショックそのものでした。 絶対音感にも無縁ですし、シャープやフラットがいっぱい付いている楽譜には「半音上げてくれたら楽なのになぁ」と願うだけの私。 もちろん、過去に指導を受けた方から“調性”の話を聞かなかったという訳ではありません。 今、松戸フィルで指導を受けている指揮者の先生からも、耳が痛くなるほど「ここはEs-dorでしょ!なぜもっと堂々と弾けないの?エロイカの冒頭と同じでしょ!」と、調性の持つ表現性について言われ続けてますし、札幌でお世話になっている指揮者の先生にも「ここは何調?」としょっちゅう質問を受け、その都度「判らない、、、知らない、、、」の世界。 「そんなの知らなくても良いじゃないか」と密かに心の中でつぶやいてました。 4才でオルガン教室に通い、何かしらの楽器に接し続けて早や44年。 何となく判ったような“つもり”でいましたが、この年になってようやく体験する事が出来、その意味が判りました。(汗) スクリャービンが、この24の調性ひとつひとつ色と意味をつけていったそうですが、 C 赤 人間の意志 G 橙 創造の戯れ D 黄 喜び A 緑 物質 E 空色 夢 H 青 瞑想 Fis/Ges 青菫色 創造性 Cis/Des 紫 創造する精神の意思 As 菫色 物質に対する精神の働き Es 肌色 人間性 B 灰色 強い欲望と情熱 F 深赤 意思の多様化 調の持つ“色”をイメージしてこれからは演奏してみたいものです。 遅まきながら世界が拡がったような気がしました。 ただ、素朴な疑問ですが、時代によってピッチが大きく変化してきたのに、共通の“色”が出るのはなぜなんでしょう? 半音以上の差はありますよね。 |
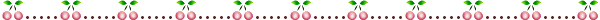 |
| HOME|音楽室|びよらのつぶやき日誌|リンクの広場|プロフィール|掲示板〜びよらの広場 |
|
